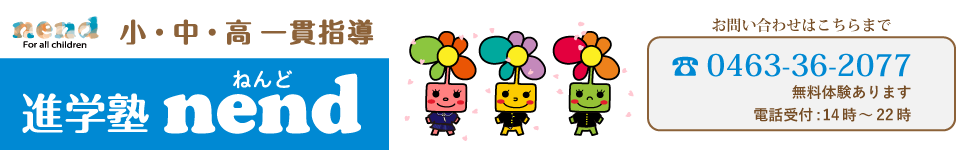叱られて
子どものころの僕はいっぱしの悪がきだったので、叱られた経験はたくさんあるはずなのだが、思い出そうとしてもとんと思い出せない。叱られている光景は浮かぶのだが、はてさてなぜ叱られたのだろうか。あるいは子どもというものはみんなそうで、自分がした過ちではなく、ただ叱られた事実だけがしこりのように残っているだけなのかもしれない。
ともかく、母親の前で正座させられ、延々と叱られながら、自分がどんどん小さくなっていき、そのうち平衡感覚がうしなわれて、自分が座っている畳が斜めにかたむいて、自分はそこから部屋のすみのほうへと滑っていくのではないか、という感覚だけを覚えている。
叱られた思い出で一番覚えているのは、高校2年生の修学旅行のときのことだ。
そのころの僕といったら人当たが良く、明るく愛嬌があって、大人には好かれていた。授業中に寝てばかりいたけれど、茶目っ気ある表情で心から謝罪するふうを装うことで、上手く立ち回っていた。要領がいいのだ。
その夜も、本来なら参加すべき修学旅行の班長会議をサボったあげく、担任のK先生に呼び出しを食らっていた。
K先生はいつも僕よりずっと勉強ができない子を構っていて、僕がからみに行ってもあんまり構ってもらった記憶がない。普段は面白いけれど、怒るときは爆撃機のようにドカンと怒る先生だ。
でもそのときは違った。落語の八つぁんのようにペコペコと神妙な表情をつくる僕を、冷たい目で見つめて言った。
「ミヤシタ、お前は要領がいい。そしてずるいやつだ。俺はお前みたいなやつが大嫌いだ」
およそ担任の言うセリフじゃないぞと苦々しく思ったけれど、そのときのことはずっと心のどこかに残っていて、潮が引けば現れる腐った杭のように、何度も胸のうちに思い返した。
――― そーかい。そりゃ結構なことだ。ならアンタの言う通りに不器用に生きてやるさ。
なんとなく反抗心からそう誓い、それから僕は生き方が確かに不器用になった。
あのときK先生の言ったメッセージを、僕は間違って受け取ったかもしれない。
それでもK先生が心から自分のことを思い叱ってくれたのだということは伝わった。
叱るということは容易く、伝えることは難しい。
- PREV
- Nend Community News 2017-1月号 電子版
- NEXT
- 個別指導というもの